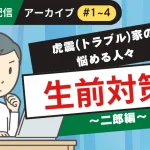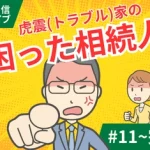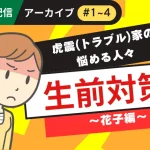LINE連載 「虎震(トラブル)家の悩める人々~生前対策・一郎編」アーカイブ(#5〜#9)
公式LINEで連載配信している「虎震(トラブル)家の悩める人々~生前対策・一郎編」のアーカイブページです。
各エピソードの概要と共に、相続に関するトラブルやその解決策を学ぶことができます。気になるエピソードをチェックし、ぜひLINEでの連載配信にもご登録ください!
目次
虎震(トラブル)家の悩める人々~生前対策・一郎編⑤

「一郎の遺言のポイント①」
今回は、一郎が遺言作成に向けて動き始めた際に郷先生が述べた主要なポイントについて解説します。みなさんも遺言書を作成する場合は参考になさってください。
1. まず、財産の全体把握
遺言作成の第一歩は、自身の財産がどのように構成されているかを明確に把握することです。
一郎の場合は、現金、預貯金、父から継いだ自宅不動産、経営している会社の株式など、あらゆる資産を一覧にして、何がどれだけあるのかを確認することから始まります。
2. 渡したい人、渡したい財産の仕分け
次に、具体的に誰にどの財産を渡すかを仕分けることが重要です。
たとえば、事業を承継するべき人、生活の基盤を支えるために現金を多めに渡すべき人など、それぞれのライフステージに応じた遺産配分を考える必要があります。
3. 渡す相手が決まらない財産はとりあえず保留
すべての財産がスムーズに渡す相手を決められるわけではありません。遺言作成時に、誰に遺すべきか迷う財産は、遺言作成時まで保留しておきましょう。
虎震(トラブル)家の悩める人々~生前対策・一郎編⑥

「遺言作成の重要なポイント②」
前回に続いて、一郎が遺言作成の準備を進める中で、特に注意すべきポイントについて解説します。今回は、渡す予定だった人が先に亡くなった場合の対応です。
■財産を遺したい相続人等が先に亡くなった場合~「予備的遺言」
遺言を作成する際、財産を相続させる相続人等が、遺言を執行する前に亡くなってしまうリスクにも備える必要があります。
この場合、先に亡くなった相続人等の部分の遺言書の記載は無効となります。その結果その財産については、遺産分割協議(話し合い)となってしまい、せっかくの遺言が台無しになってしまいます。
例えば、一郎が今の奥さんに特定の財産を遺したいと考えている場合、先に奥さんが亡くなった場合にその部分が無効にならないようにしておくべきです!
「もし妻○○が先に亡くなっている場合は、長女○○へ相続させる」などと記載しておく必要があり、この規定を「予備的遺言」と言います。
虎震(トラブル)家の悩める人々~生前対策・一郎編⑦

「遺言作成の重要なポイント③」
今回は、遺言の実行を確実にするために欠かせない「遺言執行者」について解説します。
遺言執行者は、遺言の内容を忠実に実行する責任を負い、遺産分割や財産の引き渡しをスムーズに進めるための重要な役割を担います。
1. 誰を遺言執行者に選ぶか?
この点、信頼できる家族や親族を選ぶことも考えられますが、感情的な対立や相続争いに発展するリスクが伴います!
特に事業経営者の相続では、相続内容が複雑になり専門的な知識が必要な場合が多いです。よって、第三者である専門家を選ぶことが有効です。
2. 専門家は個人?法人?
個人の専門家は、人的なつながりがあり信頼できる一方で、その人自身が病気や死亡などで対応できなくなる可能性があります。
他方、法人の専門家を選べば、担当者が変更になっても法人として業務を継続できる限り安心感があります。
よって、リスクを避けたい場合には、法人を遺言執行者として指定するのが賢明な選択と言えるでしょう。
虎震(トラブル)家の悩める人々~生前対策・一郎編⑧

「ポイントはわかったけど・・」
郷から遺言作成のポイントを伝授された一郎は早速郷と遺言の打合せに入りました。
がしかし。。。
「そうは言っても、すべてを決めるのは難しいですね…」と、一郎はため息をつきながら言いました。
郷は穏やかに微笑みながら、
「一郎さん、無理にすべてを今、完璧に決める必要はありませんよ。とりあえず、簡単な遺言書を作成するだけでも大きな一歩になります!」
と優しく語りかけました。
「でも、途中で気が変わったらどうすればいいんでしょうか?」
と一郎が尋ねると、郷は力強くうなずき、
「遺言は何度でも作り直すことができます。『やっぱり違うかな』と思った時には、新しい遺言を作成すれば、全部撤回して変更したら全部、一部変更した場合はその一部が過去の遺言は無効になりますから、安心してください。」
と説明しました。
さらに郷は、
「決まらない部分については、まず無難な行先を指定しておいて、後で考えがまとまったら調整すれば良いんです」
と付け加えました。 具体的な行動を後回しにせず、まず基本的な形を整えることだと伝えたかったのです。
一郎は少しずつ気が楽になり、
「とりあえずでも遺言を作っておけば、万が一のことがあっても家族が混乱しない、ということですね。」
と納得し始めました。
「その通りです。一郎さんが遺言を作成することで、家族が不安を抱えたり、相続手続きで争うリスクが減ります。家族のために一歩踏み出すことで、ご自身も安心できますよ!」
と郷は励ましました。
一郎は目の前の郷に感謝の気持ちを抱き、
「よし、まずはシンプルな形で遺言書を作ってみようと思います!」
と力強く決意を表しました。
虎震(トラブル)家の悩める人々~生前対策・一郎編⑨

「とりあえず、妻にすべて任せよう」
一郎は郷にアドバイスをもらいながら、まず「妻にすべての財産を遺す」という内容で遺言を作成することに決めました。
これならば、もし自分に何かあった場合でも、最愛の妻が財産を引き継いでくれるという安心感が得られるからです。
予備的遺言は、「もし妻が先に亡くなっていたら、妻との間の娘へ相続させる」です。
遺言執行者は、郷が代表の行政書士法人ジャパン相続センターを指定しました。
郷はその意図を確認しながら、遺言書に必要な形式や細かい手続きを説明し、
「これで一応の形が整いましたね。会社の株についても、ひとまず奥さんで大丈夫。オーナーは奥さんで、実際の経営者は今の取締役に指定することも可能です。
あとは、もし気が変わって内容を見直したくなったら、また新しい遺言を作成すればいいだけです。特に一郎さんの場合、状況が変わったら柔軟に対応できるのが良いところです!」
と付け加えました。
一郎はほっとした表情でうなずきました。
こうして、一郎は自分の中で一つの区切りがついたように感じ、肩の荷が降りたような気持ちで事務所を後にしました。
一郎は、ふと
「あのまま何も準備をしていなかったら、今頃、心のどこかでずっと不安を抱え続けていたかもしれないな…」
と思い返しました。
やはり、少しでも未来のことを考えて備えることで、自分も周囲も安心できるのだと実感したのです。
次回からは、二郎が自分自身の終活について悩み、行動していきます。お楽しみに!
相続に関するトラブルやその解決策を学ぶことができる事例を、LINEでの連載配信しています!ぜひ、ご登録ください!